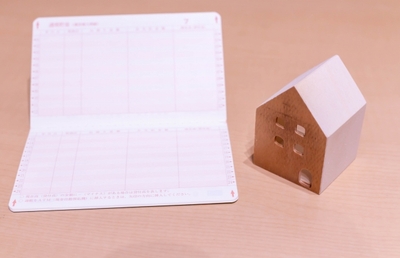後悔しない家づくりの心得
注文住宅の総額の内訳はなにがある?を解説します!
この記事をご覧の皆さんは
「注文住宅の総額の内訳について知りたい」「注文住宅の費用を抑えるポイントについて知りたい」
このように思われる方は多いと思います。
そこで、今回は注文住宅にかかる費用と、費用を抑えるためのポイントについて解説します。
□注文住宅にかかる費用の内訳について解説
大まかに把握しておくだけでも費用計画がグッと立てやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
1つ目は本体工事費用です。
これは建物そのものにかかるお金のことです。
庭や駐車場などの外構工事は含まれず、建物のみの建築費が含まれます。
広告で見かける費用はこの本体工事費用を指している場合が多いですが、後からいろいろ増えてくる会社さんもあるようですので、どこまで入っているのか、入っていないのかを確認される事をお勧めいたします。
総費用の80%から85%を占めており、たとえ広告では2000万円の家と謳っていても、実際は500万円ほど高くなることも少なくありません。
勘違いしやすい部分なので十分に注意そして確認してください!
2つ目は別途工事費用です。
これは建物以外にかかる費用のことでガスや水道、駐車場、庭、エアコンなどにかかる費用です。
目安として総費用の5%から10%と考えておきましょう。
ただし土地などの家を建てる条件によって大きく変動するので、ご自身の注文住宅の条件を把握したうえで費用を考えた方が良さそうです。
3つ目は諸費用です。
これは現金で支払うお金のことで登記費用や税金、住宅ローン、保険料などが含まれます。
その他にも家具や家電の購入費用などもあります。
全体の5%位を占めますが、条件によって変わるのでできれば少し多めに見積もっておくことが望ましいです。
□費用を抑えるポイントについて
1つ目はあらかじめ予算の内訳を決めておくことです。
理想の家を建てたいと思うあまり、どんどん予算オーバーしてしまうことも珍しくありません。
できれば最初のうちに予算の内訳を決めておくことをおすすめします。
計画的に注文住宅の建設を進められるので、予算を抑えたい方は参考にしてください。
2つ目は税金控除や補助金について把握することです。
一定の要件に該当すれば税制優遇や補助金などを利用できます。
地域や自治体が支給する補助金について事前に調べておきましょう。
□まとめ
この記事では、注文住宅の総額の内訳について解説しました。
この記事を注文住宅を考える際の参考にしていただけると幸いです。
2022年7月31日
バリアフリーをお考えの方へ!家の中をご紹介!
この記事をご覧の皆さんは
「バリアフリー住宅って何だろう」「バリアフリー住宅を作るためのポイントについて詳しく知りたい」
このように思われたことはありませんか?
そこで、今回はバリアフリー住宅にまつわる様々な情報をご紹介します。

□バリアフリー住宅とは?
バリアフリー住宅とは、障がい者や高齢者が快適に住めるような設備やシステムを備えた住宅のことです。
段差などの支障となるような障害をあらかじめ取り除くことで快適さを実現します。
また介護者も安心して介護できるような作りになっています。
実は家庭内の不慮の事故による死亡者は多く、2015年の調査では交通事故で死亡した数を2倍も上回るほどです。
特にヒートショックに関する溺死や転落死などの事故が家庭内で頻発しています。
このような事故を防ぐために、温度差のない高性能の家にする事をはじめバリアフリー住宅は浴槽や浴室内に手すりを取り付けたり廊下が滑りにくい素材で作られていたりなど、様々な工夫が施されているのです。
次はバリアフリー住宅の事例についていくつかご紹介しましょう。
1つ目は玄関のバリアフリーです。
段差をなくすことで車いすの出入りが楽になり、杖をついた方にも楽に利用いただける作りになります。
またスロープを設けると転倒の危険性が減るのでおすすめです。
雨の日は地面が濡れていることも多いので、スロープの素材や勾配にも注意すると良いでしょう。
2つ目はトイレのバリアフリーです。
寝室のそばに設置することでヒートショックなどの事故を防げます。
また外から鍵を開けられるようにすると、トイレの中でもしものことがあったときにも素早く救助できます。
3つ目は浴室のバリアフリーです。
手すりを設置したりバスタブや床を滑りにくい素材にしたりすることで、浴室内の転倒のリスクを減らせます。
浴室も玄関と同じように段差をなくすことでより安心してご利用いただけます。
□バリアフリー住宅のポイントを解説!
1つ目は介護者の居室近くにLDKや浴室、洗面、トイレを配置することです。
こうすることで家全体へのアクセスが容易になり、移動が大変な高齢の方も安心して行き来できます。
介護者もすぐにサポートできるので安心ですよね。
2つ目はオール電化にすることです。
高齢になると火の不始末で火事になる危険性もあります。
念には念を入れてオール電化にすることをおすすめします。

□まとめ
この記事をバリアフリー住宅を考える際の参考にしていただけると幸いです。
2022年7月30日
介護しやすい家の特徴を解説!新築をお考えの方は必見!
この記事をご覧の皆さんは
「介護しやすい家を作りたい」「バリアフリーリフォームの他の事例についても知りたい」
このように思われたことはありませんか?
そこで、今回は介護しやすい家の特徴と、バリアフリーリフォームについて解説します。
□介護しやすいバリアフリーの家の作り方とは?
高齢者になってから「バリアフリーリフォームをしておけば良かった」と後悔される方も少なくありません。
家をお持ちの方は余裕があるときにバリアフリーリフォームをしておくことをおすすめします。
1つ目はトイレを寝室のそばに配置することです。
寝室のそばにトイレを作っておけば高齢者になってからでも安心です。
なぜなら、年齢を重ねるほどトイレの頻度が増えますし、夜間だと転倒のリスクも高まるからです。
冬はヒートショックの恐れもあるので、なおさら寝室のそばにトイレがあると嬉しいですよね。
イズムの家ではヒートショックの心配は皆無です。
2つ目は洗面台の高さに注意することです。
歳を重ねると車いすが必要になることもあります。
最初から車いすでも対応可能な洗面台を作っておくと、リフォームをしなくても済みます。
少しためらいがある方は、洗面台の近くにベンチや椅子を設置できるスペースを確保することもおすすめです。
3つ目は廊下の幅です。
車いすでも動けるくらいの幅を確保しておくと安心でしょう。
廊下を広めに取ると介護者と介護される方が並んで歩けるので、たとえ車いすを使用しなくても介護しやすい家づくりを実現できます。
また将来的に手すりを付けたいとお考えの方は下地を入れておくこともおすすめです。
□バリアフリーリフォームの事例について
1つ目はトイレの介護リフォームです。
トイレのドアを引き戸にすることで、万が一部屋内で体調不良になってしまってもすぐに救助できるような作りにすることができます。
2つ目は玄関の介護リフォームです。
玄関は移動が激しい場所なので、けがを防止するためにもリフォームを入念にしておきたいところです。
段差をなくしてスムーズに移動できるようにすると良いでしょう。
□まとめ
高齢者になってからバリアフリーリフォームをしておけば良かったと後悔することのないよう、事前にリフォームを検討しておきましょう。
この記事をバリアフリーリフォームをする際の参考にしていただけると幸いです。
2022年7月29日
掃除が楽な家について解説します!掃除にお悩みの方は必見!
この記事をご覧の皆さんは
「掃除が楽な家について詳しく知りたい」「掃除しやすい家の特徴について知りたい」
このように思われたことはありませんか?
そこで、今回は掃除が楽な家の特徴と、掃除が楽な家づくりの方法についてご紹介します。
家づくりにおいて見栄えを重視するのはもちろん大切ですが、掃除のしやすさを意識して間取りを考えることもおすすめです。
□後回しになりやすい掃除のしやすい間取りのポイントについて
1つ目は凹凸の少ない間取りにすることです。
家の中に凹凸や段差が多いと、その分掃除の手間が増えて汚れや誇りが溜まりやすくなります。
毎日メンテナンスをすることを想定して、なるべく凹凸が少ない間取りになるように設計しましょう。
2つ目はコンセントの位置を考えることです。
掃除機をかけるとき、掃除したい場所までコードを伸ばすことが大変と悩まれる方も多いです。
掃除を楽に済ませられるよう、コンセントの位置と数は最初からしっかりと考えておきましょう。
ポイントは実際に掃除している様子をシミュレーションすることです。
3つ目は洗濯動線や掃除動線を意識することです。
洗濯機のある脱衣所や洗面所は家事動線に大きく影響します。
おすすめはキッチンと脱衣所、洗面所を同じ場所にまとめることです。
掃除しやすくなるように普段の動線も意識しましょう。
□掃除を楽にするための家づくりのポイントの中でも今すぐにでもできるような工夫について
1つ目は収納を適材適所に置くことです。
収納が大容量だとしても使う場所が動線上にないと掃除するときに不便です。
必ずしも大容量の収納が便利とは限りません。
収納はどこにどれくらい必要か明確にしたうえで設けましょう。
2つ目は家具やカーテンの色を工夫することです。
家具やカーテンの色を明るめにすることで埃による汚れを目立たなくできます。
色だけではなく形状や仕上げなども汚れがつきにくい種類があるので、これから購入される方は意識してみてください。
□まとめ
掃除しやすくなる家を作るためのポイントは凹凸の少ない間取りにする、家事動線を考えるなどが挙げられます。
掃除を楽にする家の作りは後々の時間短縮にも繋がるので最初から意識しておくことをおすすめします。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
2022年7月28日
住みやすい家づくりを目指す方へ!生活動線を考えることが重要です!
この記事をご覧の皆さんは
「住みやすい家づくりをしたい」「生活動線はどのように考えれば良いのだろう」
このように思われたことはありませんか?
そこで、今回は生活動線についてと、生活動線以外に気を付けたいポイントについて解説します。
□生活動線とは?
快適な家の条件として「生活動線が考えられている」ことが挙げられます。
生活動線とは朝起きてから就寝するまでの一連の動きを線であらわしたものです。
生活動線が考えられていないと以下のような不便が生じます。
・玄関からキッチンまでの距離が遠く、買い物を運ぶのが毎回大変
・部屋を何度も行き来する必要がある
・浴室に行くたびにリビングを通る必要があるので来客時に不便を感じる
このような失敗をしないためにも、家を作る前に生活動線をあらかじめ考えておきましょう。
生活動線には3つの種類があります。
1つ目は家事動線です。
これは炊事や洗濯などをするときに通る道のことで、負担が少なくなるような間取りにすることがポイントです。
例えば炊事や洗濯をするために外からの出入りを意識できると良いでしょう。
2つ目は衛生動線です。
これは洗面所やトイレ、浴室などに行くために使う通り道のことを指します。
プライバシーや掃除のしやすさを考えて、なるべく来客に見られない間取りにしたり、水回りを一カ所にまとめたりなどの工夫をしましょう。
3つ目は通勤動線です。
これは朝起きてから通勤、通学するために玄関を出るまでの道のことを表します。
朝忙しい時間帯に効率良く動けるような間取りにするのが重要です。
玄関先に収納場所を設けたり、洗面所のスペースを広めに取って混雑を避けたりなどの工夫ができます。
□生活動線以外に気を付けたいポイントを解説!
快適な家を作るには生活動線以外にも注意すべき点があります。
1つ目は収納について慎重に考えることです。
容量だけでなく場所まで考えられると快適な暮らしになるでしょう。
収納を考える際もなるべく動線を意識できると良いですね。
2つ目は視線や音、熱などを考慮することです。
これらは設計図だけでは判断できません。
専門家にアドバイスをもらいながら一緒に考えるようにしましょう。
□まとめ
この記事では、生活動線の考え方について解説しました。
快適な家づくりを実現させるために、生活動線は必ず意識するようにしてください。
この記事を住みやすい家づくりをする際の参考にしていただけると幸いです。
2022年7月27日